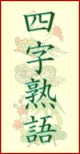重要語の意味
万有=「ばんゆう」と読み、宇宙にあるすべての物。万物。
引力=「いんりょく」と読み、2つの物体が互いに引き合うちから。
万=すべて。たへん多い。
有=ある。もっている。
引=ひく。ひきよせる。
力=ちから。はたらき。
物体=「ぶったい」と読み、人の目で確認できるもの。形を成しているもの。
重力=「じゅうりょく」と読み、地球上の物体が地球の中心に向かって引かれていくちから。重さを生じさせるもの。
積=「せき」と読み、2つの値をかけ算した結果の値。例えば、3×2=6。
比例=「ひれい」と読み、イコールで関係している数式の片方の値が増えれば同じように増えること。
二乗=「じじょう」と読み、同じ数値をかけ算すること。例えば、2×2=4。
反比例=「はんぴれい」と読み、等式上で逆数となって変化すること。
ニュートン=イギリスの物理学者、数学者、天文学者。プリンキピアで天体の運動を説明した。[1642-1727]。
プリンキピア=ニュートンが書いた「自然哲学の数学的原理」という名の本。この本の第三巻で天体の運動を万有引力の法則によって説明した。
コペルニクス=ポーランドの天文学者。1543年に「天体の回転について」で地動説を示した。[1473-1543]。
地動説=「ちどうせつ」と読み、地球などの惑星が太陽の周りを動いているという説。コペルニクスが提唱した。
ガリレオ=イタリアの天文学者、物理学者。天体観測によって木星の衛星や金星の満ち欠けなどを発見し地動説を支持した。[1564-1642]。
ケプラー=ドイツの天文学者。惑星の運動に関するケプラーの法則を導き出した。[1571-1630]。
天動説=「てんどうせつ」と読み、地球を中心に太陽や月、星などが動いているという説。キリスト教では長くこの説が常識とされていた。
第三法則=「だいさんほうそく」と読み、ケプラーが惑星の観測結果から導き出した法則の3つ目のもの。
「太陽と惑星の平均距離の三乗と惑星の公転周期の二乗の比は一定となる」。
惑星=「わくせい」と読み、太陽の周りを公転している星。恒星とは違い複雑な動きをする星。水星、金星、地球、火星、木星、土星など。
太陽=「たいよう」と読み、毎朝、東の空からのぼって昼間、明るく地上を照らす天体。夕方、西の空に沈んでいく。
|